2008年のアメリカ大統領選挙の直前、バラク・オバマ(Barack Hussein Obama, Jr.)が圧倒的に優勢だったにもかかわらず、「ブラッドリー効果がある」と評価に慎重だったメディアもあった。これは、1982年のカリフォルニア州知事選挙における、黒人のT.ブラッドリーと白人のG.デュークメジアンの一騎打ちの際の選挙民の投票行動に、アンケートの結果と実際の結果との差が生じたことから考察された考え方である。このとき、事前の世論調査では、ブラッドリーが圧倒的有利だったが、実際の選挙では、ブラッドリー支持を表明していた白人有権者がデュークメジアンに投票し、ブラッドリーは敗れてしまった。これは、事前の世論調査に対して、白人が「デュークメジアンに投票する」というと、人種差別主義的と思われるかもしれないので「ブラッドリーに投票する」と答えたからではないかと解釈されている。このような投票行動を「ブラッドリー効果」という。実際、2008年の大統領選挙でオバマは勝ったが、事前の予想より得票が伸びなかった州もあった事実がある。逆に、黒人が多い地域では、逆ブラッドリー効果が起こることもある。
ブラッドリー効果と似たものに、「アンケート実施者によく思われたい」という意識の反映があり、そこには国民性も見てとれる。1995年のTIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study 国際数学・理科教育動向調査)が行った「自分の数学の成績は?」というアンケートによれば、例えば「大変良い」と答えたアメリカの生徒のグループは34%もいるが、その平均点は534点だった。また、「良い」と答えたグループは52%もいて、その平均点は491点である。一方、日本の「悪い」と答えたグループは45%もいて、その平均点は577点、また「大変悪い」と答えたグループは10%で、その平均点は523点となり、アメリカの「良い」と答えたグループよりも高いのである。東アジアの生徒においても、同じような回答が得られている。
つまり、日本や東アジアの生徒は「できない」=「もっとできるようになりたい」と答えることがよいことである一方、欧米系では、「実際はできなくとも、前向きに答えることが正しいこと」であり、国民性の差異が見てとれる。
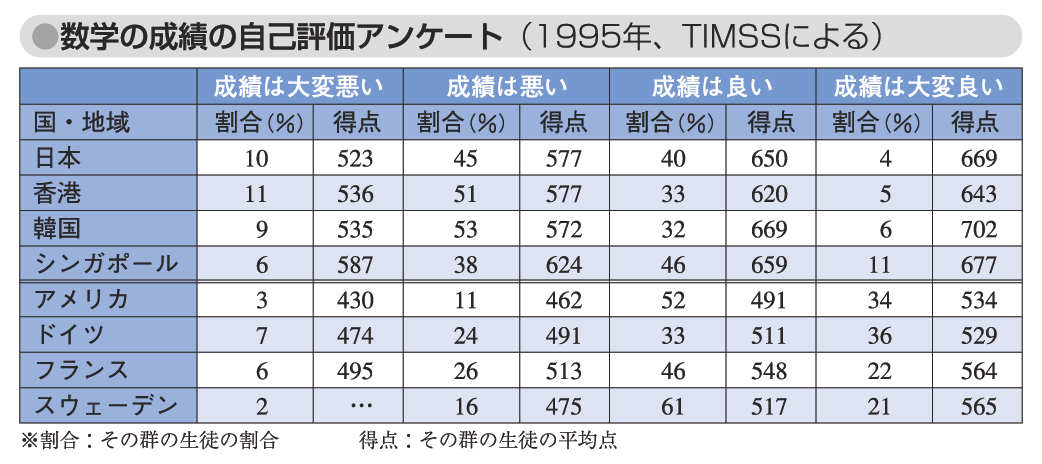
表「数学の成績の自己評価アンケート」