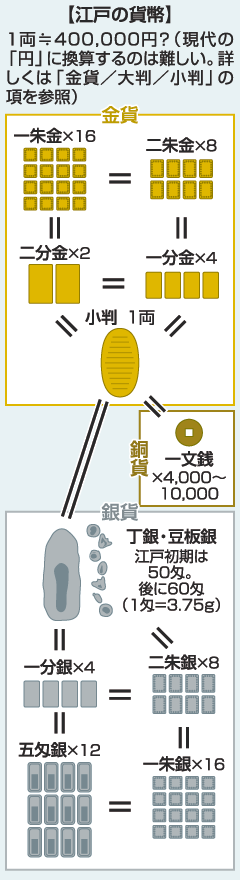「金魚」は、元は「錦魚」と書かれ、江戸初期には富裕な者の贅沢(ぜいたく)だったが、宝暦(1751~64)のころからは金魚売りの露店も出て、一般庶民の間にも広まった。江戸、京都、大坂の三都ともに金魚を楽しむ風習があり、特に町々を売り歩く金魚売りは、夏の風物詩となっていた。現代の金魚すくいでもおなじみの「和金(わきん)」のほか、尾と腹が大きく、つねに頭を下にして泳ぐ「蘭虫(らんちゅう)」も扱われ、江戸では特に「丸子(まるっこ)」といった。また、腹が大きくなく、尾の大きいものは「朝鮮」と呼んだ。これらは尾が三尖で、紅、白、紅白、黒斑などがあり、「蘭虫」や「朝鮮」の珍しいものは、3両から5両もした。縁日では、桶を並べて金魚を売る業者がおり、これを買った者は「金魚玉」と呼ばれるガラスの容器に入れて持ち帰り、軒につり下げて鑑賞した。室内では、通常は水を張った盤に入れて、上から見るものだったが、幕末の浮世絵には、現在のものに近いガラス製の水槽が描かれたものもある。