中国医学の影響下に発達した日本独自の医学。7世紀以降、遣隋使や遣唐使により中国大陸から多くの文物とともに中国医学がもたらされた。永観2年(984)に成立した『医心方(いしんほう)』30巻は、漢から唐に至る多数の医学書の引用で、日本最古の医学書である。15世紀に明に留学した田代三喜(たしろさんき)は、中国・金元時代(1115~1367)に発展した金元医学を日本にもたらし、その弟子・曲直瀬道三(まなせどうさん)は日本独自の発展をもたらした。二代目・道三となる曲直瀬玄朔(まなせげんさく)の著書『医学天正記(いがくてんしょうき)』には、実際に行った診療を疾患別にまとめ、症状や処方例を書いたもので、正親町天皇(おおぎまちてんのう)をはじめとする皇族・公家・大名・庶民などさまざまな階層の患者の実名が記されている。17世紀中ごろには、古方派(こほうは)が起こり、停滞していた漢方医学の革新をめざした。日本で最初に人体解剖を行った山脇東洋(やまわきとうよう)は古方派で、世界で初めて全身麻酔をして乳がん摘出手術をした華岡青洲(はなおかせいしゅう)も古方派の門弟である。18世紀後半には蘭方が次第に影響力を増すが、華岡は漢蘭折衷(せっちゅう)を唱え、蘭方医・宇田川玄随(うだがわげんずい)の『西説内科撰要(せいせつないかせんよう)』にも医学館の漢方医・多紀元簡(たきげんかん)が序を寄せているように、漢方が優位に立っていた。しかし、19世紀になると蘭方が主流となり、明治政府は西洋医学を修めることを医師免許の条件とした。
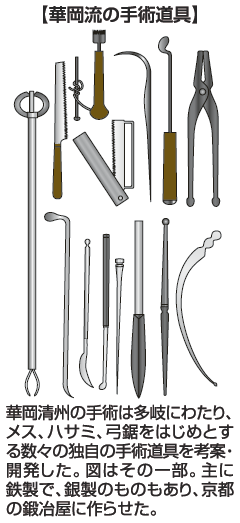
公家(くげ)
朝廷に仕える貴族や五位以上の官職にある官人。最高位の家柄は摂家。次いで、清華家(せいがけ)、大臣家(だいじんけ)などと続く。各大臣の下、文官で大納言、中納言、参議、武官で大将、中将、少将などの官職についた。
大名(だいみょう)
将軍の直臣のうち、1万石以上の知行(ちぎょう。幕府や藩が家臣に与える、領地から年貢などを徴収する権利)を与えられた武士。
蘭方医(らんぽうい)
18世紀半ばに長崎出島のオランダ商館の医師によって伝えられた西洋医学を学んだ医者。
医学館(いがくかん)
江戸にあった漢方医の医学教育機関。明和2年(1765)、奥医師・多紀元孝(たきもとたか)の願いにより神田佐久間町に設立。文化3年(1806)に火事により下谷新橋通に移転した。