身体を麻痺(まひ)させ、痛みを感じさせなくする麻酔は、外科手術に不可欠なものだった。日本では17世紀以降、南蛮・紅毛流外科医、すなわち当時「紅毛人(こうもうじん)」と呼ばれていたオランダ人やドイツ人の医師によって鎮痛のための局所麻酔が行われ、また接骨医が中国の麻酔薬を使い、18世紀半ばには治療にかなりの効果をあげるようになっていた。これらの麻酔薬は、大麻などを原料とするものであった。漢方医学の一派である古方派(こほうは)とオランダ流外科を学んだ紀州の医者・華岡青洲(はなおかせいしゅう)は、接骨医が用いていた麻酔薬を改良して、経口麻酔薬「麻沸湯(まふつとう。通仙散[つうせんさん]ともいう)」を考案した。これはマンダラゲ(朝鮮朝顔)を主成分とするものである。文化元年(1804)、華岡は、麻沸湯を用いて全身麻酔を行い、世界で初めて乳がん摘出手術を成功させ、この華岡流外科は日本外科手術の主流となった。ヨーロッパでは、19世紀半ばごろから強い麻酔作用をもつエーテル吸引による麻酔術が発達し、日本でも、幕末には、エーテルやクロロホルムなどの近代麻酔薬が導入されて、副作用のある華岡流麻酔薬は急速に用いられなくなった。
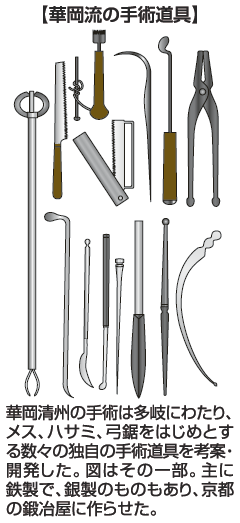
漢方医(かんぽうい)
中国医学の影響下で発達した、日本独自の医学。