原子の構造は、原子核が発見されて以降、原子核の周りを電子が円軌道を描いて回転している形で表わされたが、古典物理では受け入れがたい問題が多くあった。1913年、N.ボーアはこの軌道に量子の考えを導入し、円軌道のうちとびとびの特定のエネルギーをもった軌道だけに電子が存在するという仮説を立てて、当時、謎とされていた原子の電子スペクトルなどの問題を見事に説明することに成功した。
しかし、電子が負の電荷をもった粒子の性質だけでなく、光と同様に波としての性質をもっていることが実験で明らかにされ、電子の運動を波として取り扱う新しい力学である波動力学や量子力学の出現によって、原子の中における電子のより正確な姿が明らかにされた。それによると、電子の状態は波動関数(Ψ)で表現される。例えば、水素原子は通常は原子核から一番近い電子の軌道となるK殻の1s軌道に1個の電子がある一番安定な状態、すなわち基底状態(ground state)をとるが、その状態に対する波動関数は、
Ψ1s=Ce-r/a(Cは定数、rは原子核から電子までの距離、aはボーアモデルの軌道半径)
である。電子はもはや1個の粒子が円軌道を回っているイメージとは程遠いものであり、それに替わる電子の姿は波動関数の2乗(Ψ1s2)で表現するもので、これが1s軌道における電子が、原子核の周りの空間に存在する確率を表しているというものである。電子の存在確率は、原子核が存在する「原点」から急激に減少していき、無限遠点でゼロになり、この様子を3次元的に濃淡で表したものが電子雲である。電子雲の濃いところは電子が存在する確率が高く、薄いところは確率が低い。
電子雲は量子力学に基づく理論上の電子の姿であるが、2009年には、高電圧の印可により試料の表面に生じる電界を探る電界放射顕微鏡法(field emission microscopy)の改良型によって、炭素原子の電子軌道を電子雲の形で画像化することに成功したと報告された。また10年7月には、早稲田大学の新倉弘倫准教授らにより、高強度レーザーを利用して分子中に存在する電子の空間分布を直接観察する新技術が報告されている。
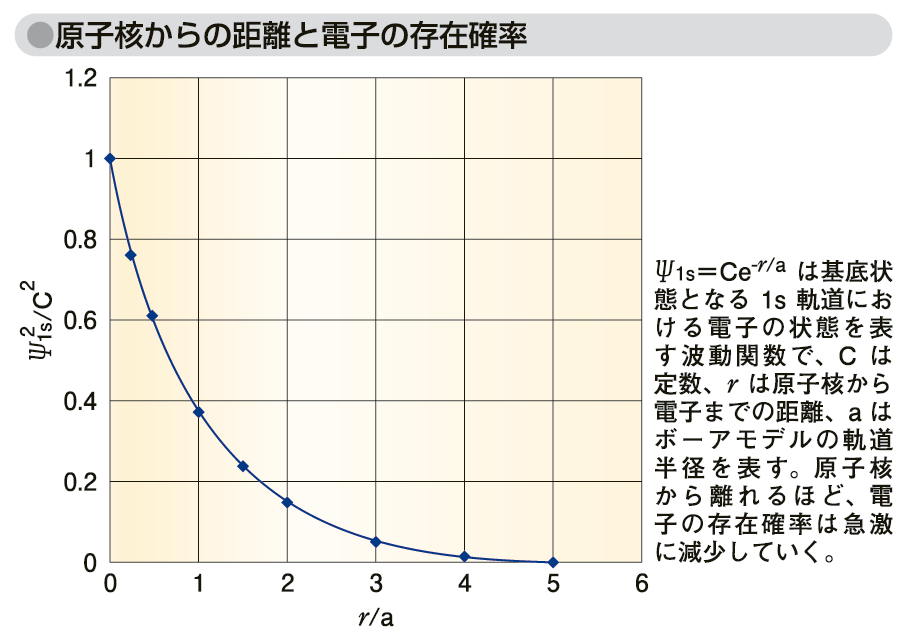
図「原子核からの距離と電子の存在確率」
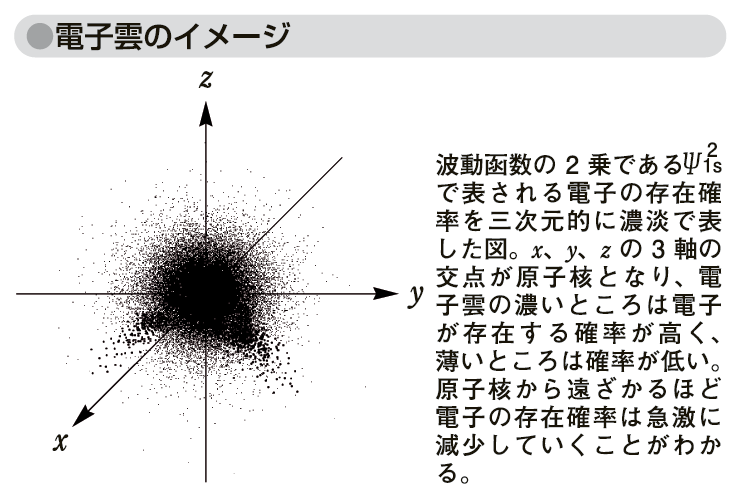
図「電子雲のイメージ」