万物には目に見えない霊魂や精霊などの霊的存在があるとする信仰。語源はラテン語のアニマ(anima)で、魂・霊魂を意味する。19世紀後半、英国の人類学者E.B.タイラーが宗教の起源・本質として提唱した学説で、宗教のもっとも単純で原始的なものは、霊的存在に対する信仰であり、これを基礎づけるのは、すべての事物には霊的存在が宿っているとする「アニミズム」であると説いた。日本の中世仏教では、比叡山の天台宗(→「密教」)を中心にして本覚思想(ほんがくしそう)が発展したが、本覚とは、有情(うじょう)すなわち人間・鳥獣などの心ある存在には、本来、覚(=悟り)の資質である仏性(ぶっしょう)が備わっているとするもので、経典などには「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」と表されている。やがてこれは有情のありのままの現実が悟りの表れだと拡大解釈されるようになり、さらに森羅万象そのものが仏性を持ち、悟りの境地にあるとされるに至る。近年ではこれを「山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)」、あるいは「山川草木悉有仏性」などと称するようになった。ここには、ありのままの天然自然を尊び、没入する心性を培っていった、日本人ならではのアニミズム的世界観の展開があり、現代のエコロジー思想との関連で注目されている。
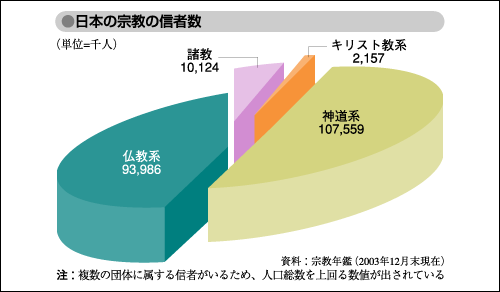
図「日本の宗教の信者数」