奈良時代、都で国家仏教を担った、三論宗(さんろんしゅう)・成実宗(じょうじつしゅう)・法相宗(ほっそうしゅう)・倶舎宗(ぐしゃしゅう)・華厳宗(けごんしゅう)・律宗(りっしゅう)の六宗を指す。平安京に都を移したのち、天台・真言両密教と区別するため、奈良を意味する「南都」の名を冠してこう呼ばれるようになった。仏教に鎮護国家を期待する朝廷は僧侶に対して学問を奨励し、奈良の諸大寺には複数の学派の教義を研究する集団が形成されて、740年代末、東大寺大仏の鋳造が完成したころには、東大寺では中国などから伝わった六つの学派を研究する組織ができていた。これが次第に体裁を整え、大仏開眼供養(→「日本の古代仏教」)の行われた752年ごろには、上記6つの「宗」が成立している。南都諸大寺では各寺院に数宗が併存し、他宗を兼学したり、他寺で学んだりすることは自由であった。東大寺をはじめとして、大安寺や薬師寺なども六宗兼学の大寺である。『華厳経』に基づく華厳宗は、学者として名高い良弁(ろうべん)が現れ、東大寺を開いたことから、その中心教学となるとともに、大仏も『華厳経』の思想に基づいて造立された。また、興福寺を中心とする法相宗、元興寺(がんごうじ)の学僧・智光が現れた三論宗の勢力も大きくなっていった。法相宗は平安時代初期には、新興の天台宗や真言宗に対する最大の対抗勢力となる。ここに学んだ学問僧徳一(とくいつ)は、空海に真言密教への疑義を呈した「真言宗未決文」を送りつけたり、誰でも悟りを開いて仏になることができるのかという「仏性」をめぐって、天台宗の最澄と論争したりした。
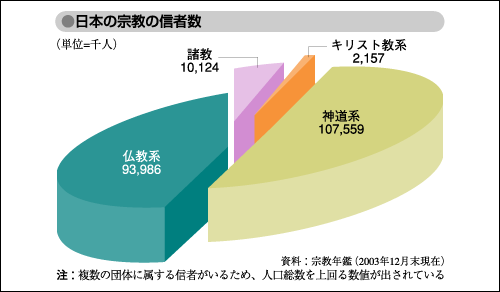
図「日本の宗教の信者数」
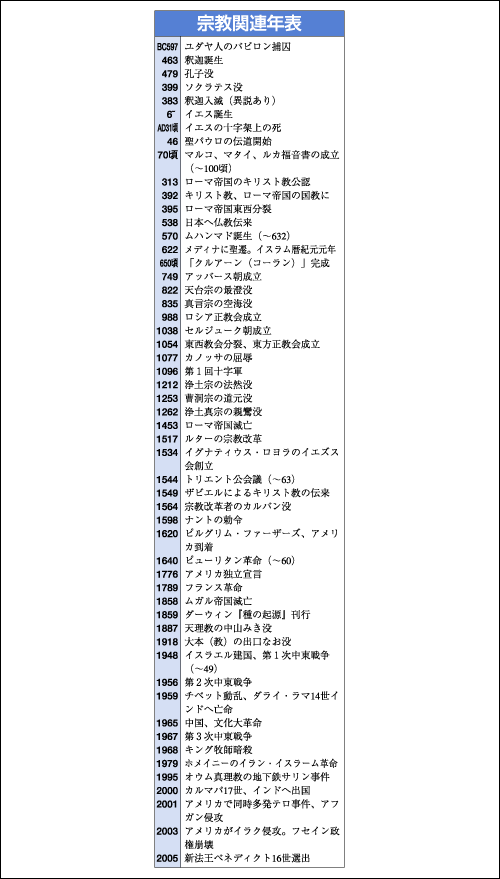
表「宗教関連年表」