日本の民俗宗教の根幹は神の祀(まつ)りと先祖の祀りであるといえる。この二つの祀りを担い、民俗宗教を豊かに発展させたのは、女性宗教者の巫女(みこ)であった。日本の神はもともと姿のない不可視の神であった。古代では神を招き寄り着かせるために依代(よりしろ)といい、巨岩や大きな樹木が用いられた。人間の依代は依坐(よりまし)といわれ、子供や女性がなる。女性は霊力があるとみなされて、神を祀ったり、神と人の間に介在して神意を告げたりすることを生業とする巫女が現れてくる。3世紀ごろの耶馬台国の女王卑弥呼はこのような巫女だったといわれる。巫女は神ばかりでなく、先祖や死霊を呼び寄せて、その言葉を告げることもある。その際、神や先祖・死者の霊が巫女の身体に侵入することになる。それを憑依(ひょうい)と呼んでいる。また、自分の魂を神や精霊の世界に訪ねさせて、その神意を受けてくることもあり、脱魂(だっこん)と呼ばれるが、日本の巫女にはきわめて少ない。憑依や脱魂をする宗教者を巫者(ふしゃ シャーマン shaman)、このような宗教現象を巫俗(ふぞく シャーマニズム shamanism)という。青森県でイタコ、福島県でワカドノなどと呼ばれる東北地方の巫女はホトケ降ろしといい、死霊を呼び寄せて、その言葉を遺族に語る。また神を憑依させる巫女は全国にみられ、民俗宗教の大きな特徴になっている。天理教の教祖中山みきや大本(教)の出口なおのように、現代ではこのような巫女から新宗教の教祖になることも多い。
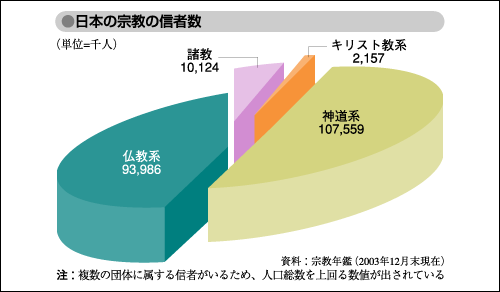
図「日本の宗教の信者数」