1603年、出雲阿国(いずものおくに)が京都で創始した「かぶき踊り」に始まる。「かぶき」は傾く(かぶく)から来た言葉で、奇抜で華美の意味だが、キリシタン風俗などを取り入れた反体制的な若者の特性をよく示しており、今日のアイドルのような熱狂的な人気が想像できる。派手な女性の踊りは風俗壊乱の理由で禁じられ、これに代わる若衆歌舞伎も男色と結びつくとして禁止、やがて野郎(前髪を落とした大人の男)歌舞伎となり、「物真似狂言づくし」として写実的な演劇の要素を取り入れて発展する。このため、女性の役も女方の男優が演じるという伝統が生まれた。元禄時代には、上方で遊郭を舞台とした男女の機微を描く和事(わごと)、江戸でスーパーマン的英雄の活躍を見せる荒事(あらごと)が生まれた。江戸時代を通して民衆に愛好され支えられた演劇として、しばしば人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)と競合関係になるが、やがてその演目を取り入れ、義太夫(ぎだゆう)、常磐津(ときわず)、清元(きよもと)などの語り物や長唄(ながうた)を生かした歌舞劇として独自の様式を生み出す。「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」などは義太夫狂言あるいは丸本物(まるほんもの)と呼ばれる名作である(丸本とは義太夫節の台本のこと)。「歌舞伎」は後世の当て字だが、こうした特長をうまく表している。文化文政期の鶴屋南北(1755~1829)、幕末から明治にかけての河竹黙阿弥(1816~93)などの名作者は、時代風俗を活写し、人間の本質に踏み込んだ作品を多く残し、演劇としての成熟度を高めた。明治に入ってからも日本演劇の中心であり続けたが、政府・文化人による洗練・高尚化の試み、生活習慣の変化などに伴い、次第に古典化の道を歩んだ。しかし新歌舞伎と称される坪内逍遙、岡本綺堂、真山青果といった作家による書き下ろし戯曲の上演、近年は3代目市川猿之助によるスーパー歌舞伎、18代目中村勘三郎のコクーン歌舞伎や平成中村座など、時代とともに歩むエネルギーは失われていない。
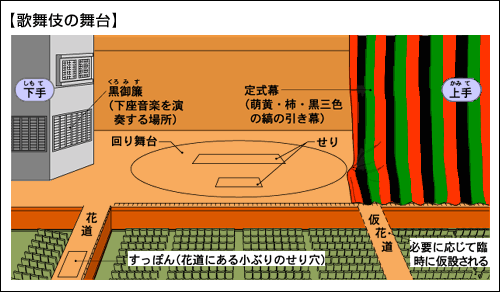
図「歌舞伎の舞台」