【7月】島尾敏雄(当時28歳・鹿児島にて)
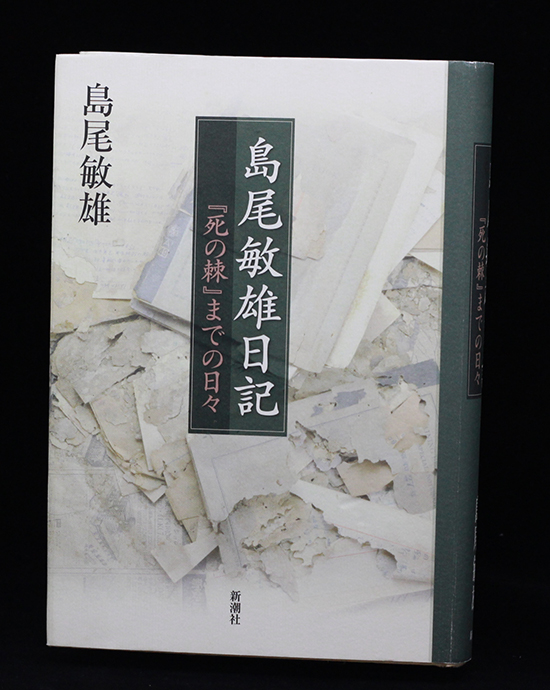
七月三十一日
(中略)
私達ノ民族ノ一ツノ大キナ試練ノ嵐、滅ビルモノハ滅ビテマコト素直ナモノダケガ残ルノダト信ジテヰル。私ハ(私の愛スルモノト共々ニ)ソノ過渡ノ時代ニアツテイクラカノオ役目ヲ荷フ。ソシテソレヲ果ス、来ル日ノタメニ、ソレガドンナオ役目デアラウトモ早問フ所デハナイ。
モウ誰モ信ジナイ、広イ世ノ中ニボクノ味方ハミホダケダ。ボクニハボクノ任務トミホダケシカコノ世ノ中ニハナイ。
『島尾敏雄日記―「死の棘」までの日々』 島尾敏雄 新潮社
【紹介】
島尾敏雄(1917~1986)は、心の病を持った妻との凄絶な生活を描いた私小説『死の棘』で知られる作家。海軍特攻の第十八震洋隊隊長として奄美群島の加計呂麻島に赴任する。そこで島の娘であったミホと出会う。厳しい訓練と敵機の襲撃といった緊迫した状況の中で二人は文をやりとりし、夜の浜辺で密会を重ね、激しい恋に落ちる。特攻戦の命令が下るが、決死の発進を待つばかりの状態のまま終戦を迎える。その後、神戸に復員し、ミホと結婚する。
島尾は終生日記を書きつづけていたと言われているが、終戦直後のものがまとまって見つかったのは、2007年のミホ夫人没後である。日記にはミホ夫人の書き込みが残っている。時を超えた一組の夫婦の痕跡は、南国での神話的な恋から、『死の棘』の生き地獄へたどり着いた男女の戦後の生の重なりを思わせる。
【解説】
日記には特攻隊長としての苦悩や読んだ本のことなどが並んでいるが、隅々にまでミホへの思いが溢れている。あまりにも若い二人の命の間際でのやり取りは痛ましくも、神話のように美しいというほかない。
状況が最も逼迫したのは、「出撃即時待機」となった8月13日から終戦の日までの数日間であった。今まさに死出の旅に立とうとする島尾を思い、ミホは特攻基地の近くの浜辺で正座し、形見の短剣を胸に抱き、彼の旅の共をする覚悟であったという。
その日のことが日記に記されている。「コンヤモオイデ、ユウベノトコロマデ」「ボクハ三時半前後アノヘンニ出テミマス。一寸シカアヘナイケレ共、一寸ダケミホノ顔ヲミレバ、ヨイノデス。ケツシテ、トリミダスヤウナコトヲシテハイケナイ。カハイヽカハイヽミホニ」(八月十四日)。国家から命ぜられた死を目前にした特攻隊員の心のうちは、後世の平和の世を生きる者には知りようがない。燃え上るミホへの思慕のうちに、彼女が与えてくれる慰撫の温かみのうちに、彼の恐れや孤独、淋しさの深さを推し量るだけだ。
出発は遂に訪れることはなかった。翌日、島尾は一言「元気デス」(八月十五日)としたためている。日記はその後、混乱の戦後の慌ただしい暮らしとともに書き継がれていく。戦後の生が彼らにとってどのようなものだったのかはわからない。運命などという安易な言葉を使うのは憚られるが、この夏の体験は島尾とミホの二人それぞれの生の深いところにぬきがたく刻み込まれたことだけは間違いない。読者は戦時下に結ばれた二人の、まさに稀有なその瞬間に立ち会うことができる。
