【8月】谷崎潤一郎(当時59歳・岡山にて)
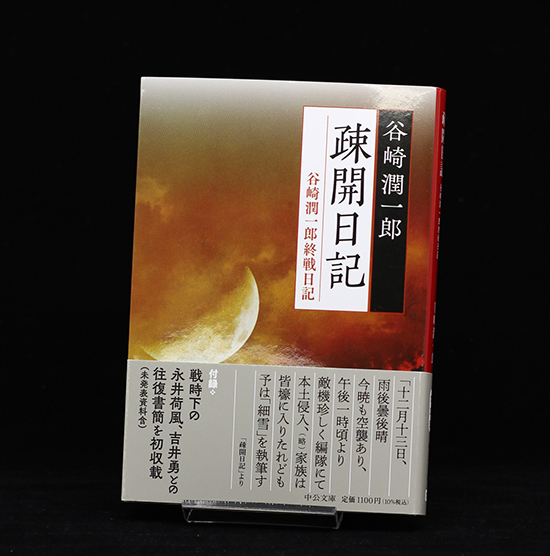
八月十三日、晴
本日より田舎の盂蘭盆なり。午前中永井氏より来書、切符入手次第今明日にも来訪すべしとの事なり。ついで午後一時過頃荷風先生見ゆ。今朝九時過の汽車にて新見廻りにて来れりとの事なり。カバンと風呂敷包とを振分にして担ぎ外に予が先日送りたる籠を提げ、醬油色の手拭を持ち背広にカラなしのワイシャツを着、赤皮の半靴を穿きたり。焼け出されてこれが全財産なりとの事なり。然れども思つた程窶(やつ)れても居られず、中々元気なり。拙宅は満員ニ付夜は赤岩旅館に案内す。
『疎開日記―谷崎潤一郎終戦日記』 谷崎潤一郎 中公文庫
【紹介】
谷崎潤一郎(1886~1965)は戦時中、岡山県津山、その後勝山に家族で疎開している。ここで谷崎は軍部から発表の差し止めをされていた『細雪』の執筆をつづけている。ドナルド・キーンからは引用する気にはなれないと断ぜられているが、流麗な文章で疎開の苦労や空襲、家人の様子、町の風物や詳細な食事の献立までが細やかに描かれている日記は、文豪のものであるかどうかに関わらず、戦時下の生を知る意味においても読みごたえ十分である。
不便さが募る暮らしのつらさは別にしても、谷崎は時局や戦争そのものに対して何ら書いてはいない。一片の心情すらも表明していない。一方で戦時下、この日記を書きつつ、同時に『細雪』のあの絢爛たる世界に没入していたことを思うと、何か空恐ろしいものを感じるほどだ。
8月15日も玉音放送を聞きに向かいの家に行くもののよく聞き取れず、帰宅して荷風の原稿を読んでいると、日本が無条件降伏したことを家人から知らされる。日記には、町の人々は興奮し、家人は涙した、としか記されていない。谷崎本人が何を思ったのか、何をしたのかは知りようがない。しかし、政治的なものに対する徹底した抑制あるいは無関心もまた、ひとつの政治的な態度であろう。
【解説】
自宅を焼失した永井荷風が、谷崎を頼ってはるばると勝山までやってくる。荷風といえば、早くから谷崎の才能を見出し、世に知らしめた恩人である。谷崎は恩人の到着を待ちわび歓待する。翌日の夜には酒を二升手に入れ、苦労して牛肉まで入手し、すき焼きを振る舞い談笑する。「談話頗(すこぶる)興あり。九時過辞して客舎にかへる。深更警報をききしが起きず」(『断腸亭日乗』)とほろ酔いの荷風も記す。終戦のまさに前日のことだ。
荷風は谷崎のところに余程留まりたかったのか、勝山に移りたい様子を見せる。しかし、谷崎は恩人の身の上を心配しながらも「部屋と燃料とは確かにお引受けすべけれども食料の点責任を負ひ難き」(八月十四日)と世話をやんわりと断っている。荷風の方はというと「事情既にかくの如くなるを以て長く谷崎氏の厄介にもなりがたし」と残念そうに記している。荷風は未完の小説原稿「ひとりごと」(戦後『問わずがたり』と改題し発表)、「踊子」「来訪者」を谷崎に託し、谷崎が用意してくれた汽車の切符と弁当を持って去っていく。8月15日のことだ。
巻末には「永井荷風との往復書簡」が収められている。日本を代表する二人の文豪の戦時下の交流に関心のある人には必読だ。
【8月】永井荷風(当時65歳・岡山にて)
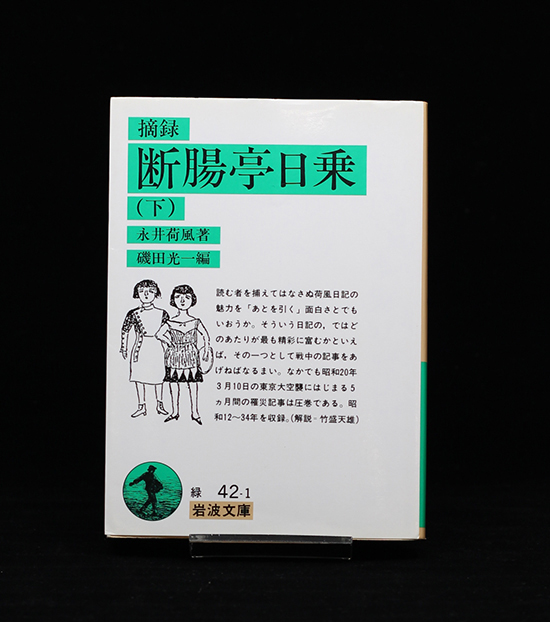
八月十五日。陰(くも)りて風涼し。(中略)新見駅にて乗替をなし、出発の際谷崎君夫人の贈られし弁当を食す。白米のむすびに昆布佃煮及牛肉を添へたり。欣喜措く能はず。食後うとうとと居眠りする中(うち)山間の小駅幾個所を過ぎ、早くも西総社また倉敷の停車場をも後にしたり。農家の庭に夾竹桃の花さき稲田の間に蓮花の開くを見る。午後二時過岡山の駅に安着す。焼跡の町の水道にて顔を洗ひ汗を拭ひ、休み休み三門の寓舎にかへる。S君夫婦、今日正午ラヂオの放送、日米戦争突然停止せし由を公表したりと言ふ。あたかも好し、日暮染物屋の婆、雞肉葡萄酒を持来る、休戦の祝宴を張り皆々酔うて寝に就きぬ。
『摘録 断腸亭日乗(下)』 永井荷風 磯田光一編 岩波文庫
【紹介】
永井荷風(1879~1959)は37歳から亡くなる年まで、大正・昭和にわたって実に41年間も日記を書きつづけた。『断腸亭日乗』は日記文学の傑作として名高く、荷風ファンでなくとも読者を魅了してやまない本書については、多くの評論や解説がある。
文語体の簡潔な文章で、天候(必ずその日の天気を記している)や日常の瑣事、訪問した場所や風物のことから、世相や時局の批評までさまざまなことが書き残されていて、読んでいて飽きることがない。
日記を読むということはその人間の私的な暮らしや行い、時々の感情や思想を覗き込むことであり、何よりもその人の存在や人間性を間近に感じることができる。この日記から伝わってくるのは、ひたすら世俗にまみれながらも世の動きに動ずることなく、虚飾も欺瞞もなく、頑迷でありながらしなやかに脈々と息づく一個の独立した精神のありようだ。
荷風は戦時中、鞄に日記を入れ、どこに行くにも後生大事に持ち歩いた。荷風にとって日記を書くことは生きる習慣であったのだろう。死の前日まで書き継いだというこの日記が荷風にとってどれほど大切であったかは、想像に難くない。
【解説】
8月15日、岡山県勝山に疎開中だった谷崎のもとを辞した荷風は、岡山駅への汽車に乗る。途中谷崎夫人が持たせてくれた弁当を食べ、そのあまりの美味しさと気遣いに喜びを表している。その後、疎開している家までたどり着いた時に、戦争が終わったことを知る。荷風が嫌いぬいていた戦争がようやく終わる。葡萄酒で祝宴を張っているところがいかにも荷風らしい。
3月の東京大空襲で荷風は罹災した。現在の港区六本木にあった自宅「偏奇館」が焼失し大量の本も失ってしまう。家の灰の中から奇跡的に谷崎から贈られた断腸亭の印を掘り出し、「罹災の紀念これに如くべきものなし」(三月十一日)と記す。空襲の体験から無一文で焼け出されて疎開するまでの間の記載は臨場感に溢れ、筆が冴え渡っている。
谷崎とは違い、荷風は戦争や軍国主義をあからさまに嫌悪し、軍人を蛇蝎のように嫌った。「東京住民の被害は米国の飛行機よりもむしろ日本軍人内閣の悪政に基くこと大なりといふべし」(一月二十四日)。「軍部の横暴なる今更憤慨するも愚の至りなればそのまま捨置くより外に道なし。われらは唯その復讐として日本の国家に対して冷淡無関心なる態度を取ることなり」(五月初五日)。荷風は、軍人のみならず、いかなる権威も新思想も嫌い、失われていく風物や美を愛し、終生にわたって市井の人間がまとう欲望と情に生きた。
