
「日本」が浮かび上がってくる
安田 三浦さんも震災やアフリカ、近現代史など多彩なテーマでノンフィクションを書かれていますが、三浦さんが意識している共通の「二文字」というのは何なのでしょうか?
三浦 私のそれは、おそらく「日本」ですね。「日本とは何か、日本人とは何か」みたいなものをテーマに据えて、日々取材を続けています。「日本」というものに光を当てるとき、多くの日本人は現在の日本列島のことしか考えていません。でも、そう遠くない過去にこの国は台湾を領有し、朝鮮半島を占領し、中国東北部には満州国という傀儡国家を持っていた。かつてこの国は大きな帝国だったのです。一方で、この夏文庫化された『太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密』(集英社)で取り上げたように、日本企業は戦後、海外へと進出し、今でもアフリカには日本名を名乗る日本人残留児たちがいます。工業立国でありながら肝心な資源を持たないという矛盾。島国で地上の国境線を持たないためがゆえに、隣国との国境線をめぐるいざこざが少ない一方で、国際感覚が身につきづらく、自分勝手な論理が比較的通用しやすい地域であるという特性。世界的に見ても極めて特殊な国だと思うのです。そんな小国で生きる一人の日本人として、「日本とは何か、日本人とは何か」という命題をずっと胸に抱えながら国内外を歩いています。
安田 なるほど。私が取材しているのも、「外国人問題」ではなく、「日本人の問題」なのでしょうね。先日、関東のある大学で学生たちにクルド人についてのイメージを聞くと、約3分の2が否定的なイメージを持っていて驚きました。ネット上にあふれるヘイトスピーチに影響されていたんです。そうしたクルド人に向けられたデマとヘイトスピーチを止めたいと思っているのですが、クルド人も一人の人間であるということを主張することが、なぜこんなに難しいんだろうかと、私は思います。
三浦さんの『太陽の子』では、アフリカの女性との間にできた子どもを置いて帰国した日本人労働者について、一方的に糾弾しているわけではないですよね。一人の非常に人間くさい労働者としての在り方みたいなものも見えてくる。どんな小さな出来事を描いても、あるいは、人間の息遣いに焦点を定めても、やっぱり社会の姿というものがその都度浮かび上がってくる――私は、優れたノンフィクションというのはそういうものだと思います。
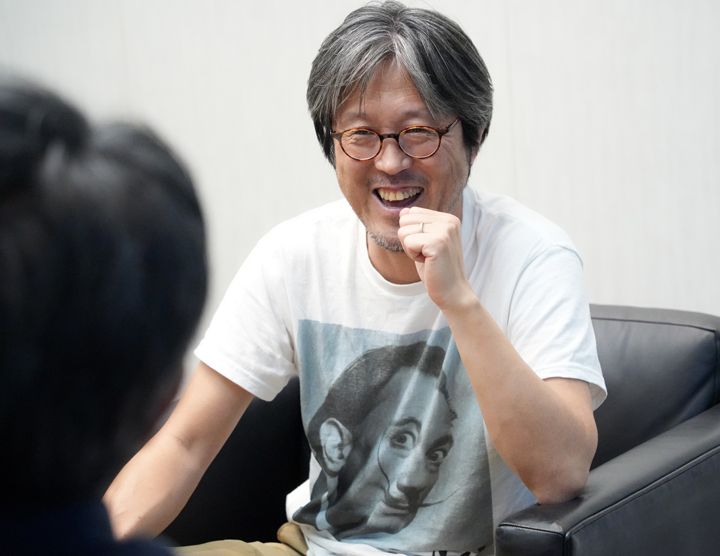
佐野眞一とノンフィクションの時代
三浦 「優れたノンフィクション」といった言葉で思い出しましたが、最近、安田さんは雑誌「プレジデント」でノンフィクション作家・佐野眞一さんについての評伝を発表していますよね。私は当然、佐野さんの本は全部読んでいるのですが、どちらかというと、佐野さんについてはネガティブなんです。安田さんはデータマンとして佐野さんを最も近くで見ていた人のうちの一人ですから、愛着ももちろんあるでしょうし、いろいろと複雑な思いをお持ちなのかなと思いますが、いかがですか?
安田 正直に言うと、佐野さんについて書くというのは、非常にしんどい作業です。例の「週刊朝日」の件以降は、やっぱり佐野さんを批判せざるを得ない。ただ、満州三部作から佐野さんのデータマンとして取材に同行したりしていたので、目の前で佐野さんが一軒一軒、戸を叩いて取材をしている姿を目にしていて、「この人はすごいな」と思ったことは事実なんです。
三浦 私からすると、佐野さんはやはり「怪物」なんですよね。ページをめくらせる筆力はあるのかもしれないのですが、佐野さんはどこか、事件や対象者を描くにあたって「知る権利」や「公益性」というものを盾に取り、たとえば事件で被害者であるはずの東電OLの女性の尊厳をこれでもかというくらいないがしろにする。私には残念ながら、佐野さんの作品からは人間に対する愛情というようなものを感じ取ることができないんですよね。
安田 佐野さんは『東電OL殺人事件』(新潮社)が爆発的に売れて以降、周囲から「先生」と呼ばれることを受け入れてしまった。私はそこが最大の失敗だと思っています。そしてそれは、ノンフィクションの凋落でもあったと思います。でも、佐野眞一という人間の足跡を追うことにより、この国におけるノンフィクションの一時代が見えてくるようにも思えるのです。ノンフィクションライターとして筆だけで成立していた最後の世代である佐野さんを通して、ノンフィクションという業界の歴史を描くことができないか。そして佐野さんを通して、自分自身がノンフィクションライターとして何をすべきなのか、しっかりと残さなければいけないと思っています。三浦さんとお話ししながらふと、『1945 最後の秘密』に登場する原爆で亡くなった元タカラジェンヌの言葉を思い出しました。
「何でも知ることです。何でもやることです。実行し、反省、そして実行です」
どう生きようとしたか──何をテーマにしようとも、最後には私自身が問われる。その覚悟を抱かせてくれる言葉でもありました。
