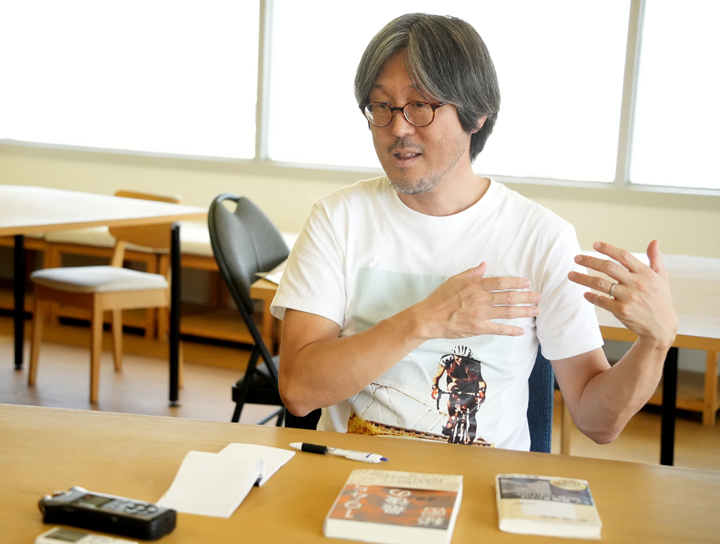
小山 私は記者になったのが2017年ですから、ちょうど第二世代と第三世代の間にいるのだと思います。いま、原爆についての話を聞けるのは、ほとんどが被爆者の方々が幼少期の頃の記憶なんです。もちろん、子どもの目から見た戦争体験はすごく貴重なのですが、戦前からどんなふうに暮らしが変わったのか、何が奪われたのかという話は、私の世代ではもう聞くことができません。
三浦 戦争の体験を直接聞くことができなくなるこれからの世代が、どのように戦争の記憶を継承していくのか。戦争体験者の証言映像があるからそれでいいじゃないかという意見もありますが、実はそれは非常に危険なんですね。証言映像というのは、証言者がカメラを常に意識するので、「正しいこと」を話そうとする。そしてそれは同時に、「切り取った事実」でもあるんです。人は往々にして、カメラが回っていないときに、「本当のこと」を話す。一緒にお弁当を食べたり、銭湯に行ったりしたときに、ふと、その人が体験した苦しさや、大切な人が亡くなったときの痛みのようなものを、泣きながら話してくれる。それは決して、カメラでは残せない「事実」であり、「告白」なんですよね。
小山 そうですね。でも実際、戦争体験者である第一世代は、もうほとんどいらっしゃらない……。三浦さんは『1945』のなかで、10年以上も前に出会った方を長く長く取材されていますよね。
三浦 そうですね。それぐらいしか、私の取りえはないから……。第4章の満州国の元官僚の方の話は、本にまとめるのに11年かかりました。最終章の「原爆疎開」については、2010年から取材しているので、15年かかっています。そうすることでようやく、取材対象者との人間的な関係を描けるようになる。新聞記事の場合、すぐに会いに行って、わかった事実だけを記事にしますが、取材対象者との人間関係を縦軸にして、その人と付き合った15年間の記録をつむいでいくことで、新聞記事とはまるで違った「作品」に昇華できる。そうした時間軸を強く意識して、とにかく時間をかけて書いたのが今回の『1945』でした。

小山 10年以上前の取材でも、古びていないのはそういうことなんですね。時間軸を取り入れるというのは、これから戦後90年に向けてやっていくべき取材のやり方なのかもしれないですね。
これからは、まだ取り残されているものに目を向けるということが、大事になってくると思います。私にとってその一つが、「黒い雨」でした。戦後90年に向けて、いま私が取り組んでいるのは「被爆二世」というテーマです。被爆二世は、被爆者の言葉を受け継ぐ存在として取り上げられます。彼ら自身も、遺伝的影響への不安とか、被爆者である親の介護を引き受けるなかでそれぞれの「原爆」と向き合い、さまざまな差別にもさらされてきました。それらをどう捉えるのか。戦後90年に向けた架け橋として、私は子孫に目を向け始めています。
「戦後100年」に向けて、戦争ノンフィクションの継承
三浦 私はこれまでずっと「戦後80年」に向けて取材や執筆を続けてきたから、いま小山さんの口から「戦後90年」という言葉を聞いて、正直、はっと目を開かされたような気がしました。確かに、「戦後90年」「戦後100年」に向けて何を書いていくのかというのは、とても大きなテーマですね……。
私は何を書けるだろう……。まだ具体的には何も思いつかないけれど、これからも「日本とは何か」についてはこだわって書き続けていきたいと思っています。かつての日本は、満州国を持ち、朝鮮や台湾、南洋諸島を占有していた、巨大な海洋国家なんですよね。そんな祖国の姿を、自分なりの経験や視座で描いていきたい。
小山 『1945』の「原爆疎開」の章で、新潟の方が戦前の日本地図について「日本海はあたかも湖のよう」と言うのが、とても面白い視点だなと思いました。
三浦 私の部屋にはいまも、富山県が発行している「逆さ日本地図」が貼ってあるんです。それを見ると、大陸から見た日本というのがとてもよくわかる。樺太から日本列島、そして沖縄から先の台湾まで、点在する島々にしか見えないんです。かつては樺太も台湾も日本だった。そのような視点でこの島々を見たときに、浮かび上がってくる「日本」を描けないかと、いつも思っています。
小山 私たちの世代は、いまニュースやわからないこともYouTubeで検索したりしています。昔と比べて新聞などの「マスメディア」の信頼はどんどん落ちていますが、そんななかでも、書籍というのはまだ信頼されていて、人に伝える媒体として希望である気がしています。
